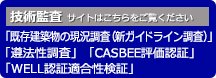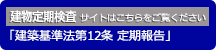��t���ԁF����9:00-17:00�i�����j�^ 9:00-17:30�i�d�b�j
TOP�y�[�W > �R������BV MAGAZINE > ���z���ȃG�l�@�̊T�v����т��̋K���[�u�i�ȃG�l�K���Ɠ͏o�j�ɂ���
���z���ȃG�l�@�̊T�v����т��̋K���[�u�i�ȃG�l�K���Ɠ͏o�j�ɂ������݃����e�i���X���ł��B |