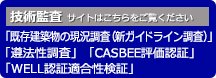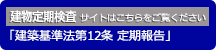TOP�y�[�W > �R������BV MAGAZINE > �Ɛk���z���̐R���s�@�I�ȕϑJ�ƖƐk���z���̐v�@�t
�Ɛk���z���̐R���s�@�I�ȕϑJ�ƖƐk���z���̐v�@�t2023/2/13up
1�D�@�I�ȕϑJ����12�N10�������z�E�{�s���ꂽ�u�Ɛk���z���̍\�����@�Ɋւ�����S��K�v�ȋZ�p����߂铙�̌��i����12�N10��17�����ݏȍ�����2009���j�v�ɂ���A�����܂ő�b�F����擾���Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ɛk���z�����A��������������������s�����▯�Ԋm�F�����@�������z�m�F���邱�Ƃ��\�ƂȂ�A�Ɛk�\�������L�����y����Ɏ���܂����B �� ����16�N9��������ʊ�Ƃ��Ă̖Ɛk���z���̃N���A�����X�K���A���K�͌ˌ��Ɛk���z���̌��ݏ�̖��ւ̑Ή�������|�Ƃ��āA����������������܂����B ������19�N6��20����������17�N11���ɔ��o�����\���v�Z���U���������_�@�ɁA����������ъ֘A�����i����12�N���ݏȍ�����1457���j�̉������s���܂����B �i1�j�\�w�n�Ղɂ������x�̑�������\�����lGs�ɂ��āA���K�͂̒n�k���ɍ̗p�ł���v�Z���@��n�Վ�ʂɊ�Â����Z�I�ȕ��@�Ɍ���i������10��1���j �i2�j�ɂ߂ċH�ɔ�������n�k���i��K�͂Ȓn�k���j�ɂ��Č������s������Gs�̐��l�Z����ۂɂ����āA�n�Ղ��t���鋰�ꂪ�Ȃ����Ƃ������Ƃ���B�����āA�n�Ւ����ɂ���Ēn���[���Ɏ���\���ȑw���ƍ�����L���A���A����①����③�܂łɌf�����ɓK������H�w�I��Ղ�L���邱�Ƃ��m���߂邱�ƁB(������10��2��) ①�n�Ղ̂���f�g���x����400���[�g�����b�ȏ�ł��邱�ƁB ②�n�Ղ̌�����5���[�g���ȏ�ł��邱�ƁB ③���z���̒����𒆐S�Ƃ��A�\�w�n�Ղ̌�����5�{���x�͈̔͂ɂ����Ēn�Ղ̐[������l�Ȃ��̂Ƃ���5�x�ȉ��̌X�ł��邱�ƁB�������A���ʂȒ����܂��͌����̌��ʂɊ�Â��X����H�w�I��Ղ���̒n�k���̑����Ɠ����ȏ�̑������v�Z�ł���ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B 2�D�Ɛk���z���̐v�@������2009���ɂ́A�Ɛk���z���̐v���@�Ƃ��Ĉȉ���3���L����Ă��܂��B�i������2�@��A��A�O���j �e�v�@�̊T�v�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B �i1�j���K�͌��z���̖Ɛk�v�@���K�́i�l�����z���Ȃǁj���z�ŁA�d�l�K��i���z��@�{�s�ߑ�3�͑�1�߂���ё�2�ߕ��тɍ�����3����ё�4�j�����ꍇ�A�㕔�\���Ɋւ���\���v�Z���Ə�����Ă��܂��i������6��3���j�B �����Ɏ�����Ȏd�l�K��͈ȉ��ƂȂ�܂��B�ڂ����͍�����3����ё�4�����Q�����������B ①�㕔�����̍ʼn��K�̏��ł́A����18cm�ȏ�̈�̂̓S�R���N���[�g���Ƃ��A���A�a 12mm�ȏ�ٌ̈`�S��200�ȉ��̕����z�Ƃ��邱�ƁB ②�Ɛk���u�̎x���ނ́A�㕔�\���̌��z�ʐ�15�u�ȉ���1�����ȏ�Ƃ���B ③�n�Ղ�1�A2��n�Ղʼnt���Ȃ����ƁB�܂��A�����ɐ�����͂ɑ��鋖�e���͓x��50kN/�u�ȏ�ł��邱�ƁB ④�גn�i�~�n���̕��ȂNJ܂ށj�ƌ��z���Ƃ̋�40cm�ȏ�Ƃ��A�l�̒ʍs������ꍇ50cm�ȏ�Ƃ���B ⑤�Ɛk���u�ޗ��́A��������ѓ_����e�Ղɍs���ʒu�ɐ݂��邱�ƁB ⑥�q�ɂ��̑�����ɗނ���ύډd�̕ϓ��̑傫�ȗp�r�ɋ�������̂łȂ����ƁB �i2�j��L�l�����z���ȊO��60m�ȉ��̖Ɛk���z���̐v�@�ϋv���W�K��i�{�s�ߑ�36���1���j�ɓK�����A���A�����ɒ�߂�ꂽ�\���v�Z�@�i������6�j�ɂ���Ĉ��S�����m�F������@�ŁA���������Ɛk�ƌĂ�Ă���Ɛk�v�@�ł��B ①�㕔�\���̌v�Z���@ ②�����\���̌v�Z���@ ③�Ɛk�w�̌v�Z���@ �i�v�Z���@�j
�i�m�F���ځj
④�Ɛk�ޗ��̐v �i�m�F���ځj
�i3�j��b�F���K�v�Ƃ���Ɛk�v�@����60m���钴���w���z���A�����60m�ȉ��Ŏ��������͂ɂ����S�����m�F�����Ɛk���z���͍��y��ʏȂ̑�b�F���K�v�Ƃ��܂��B
�r���[���[�x���^�X�̃T�[�r�X |